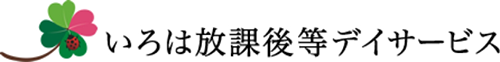「うちの子、学校の授業についていけていないみたい…」
「一生懸命やっているはずなのに、どうして読み書きや計算が苦手なんだろう?」
「もしかして、育て方が悪かったのかしら…」
大切なお子様の学習について、このような悩みを抱え、一人で心を痛めている保護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
周りの子と同じようにできない姿を見ると、焦りや不安を感じてしまうのは当然のことです。
しかし、まず知っていただきたいのは、お子様の学習の困難さは、本人の努力不足や、ましてやご家庭の育て方が原因ではないということです。
多くの場合、その背景には発達障害と呼ばれる、生まれ持った脳機能の特性が関係しています。

アットスクール平野加美駅前教室では、放課後等デイサービスを運営している発達障がい児教育の専門家として、なぜ学習の困難さが生じるのかという根本的な原因から、その解決策として注目される「個別指導」に注目しました。
なぜ「勉強の困難さ」が生まれるの?発達障害の特性を正しく理解する
多くの子どもたちが当たり前のようにこなしている「読む」「書く」「計算する」といった学習が、なぜ特定のお子様にとっては非常に難しく感じられるのでしょうか。
その答えは、発達障害の特性を理解することにあります。
発達障害は、生まれつきの脳機能の発達の違いによるもので、本人の「なまけ」や「努力不足」ではありません。
知的発達に遅れがないことも多く、特定の分野だけが極端に苦手というケースが少なくありません。
そのため、周りからは「やればできるはずなのに」と誤解されやすく、お子様自身も「自分はダメなんだ」「僕はばかだから」と自信を失ってしまうことがあります。
この見えない困難さが、お子様を精神的に追い詰める一番の原因となり得ます。

特に学習面で困難さが表れやすいのが、限局性学習障害(LD)です。
LDは、主に3つのタイプに分けられます。
LDのタイプ
- 読字障害(ディスレクシア): 文字を読むことに困難さがあります。文字が歪んで見えたり、どこで区切って読めばいいかわからなかったりするため、一文字ずつたどたどしく読む「逐次読み」になったり、行を飛ばしてしまったりします。音読をひどく嫌がる、読めても内容が頭に入ってこないといった特徴も見られますが、耳から聞けば内容は理解できることが多いです。
- 書字障害(ディスグラフィア): 文字を書くことに困難さがあります。鏡文字になったり、「わ」と「は」のような同じ音の仮名を使い間違えたり、マスの中にバランスよく文字を収められなかったりします。頭の中では文章が作れても、それを文字にすることが非常に困難です。
- 算数障害(ディスカリキュリア): 数的な概念の理解や計算に困難さがあります。数を数える、繰り上がり・繰り下がりを理解する、時計を読む、図形を理解するといったことが苦手です。
これらのLDの特性に加えて、注意を持続させることが難しいADHD(注意欠如・多動症)や、対人関係やコミュニケーションに特有の困難さがあるASD(自閉スペクトラム症)の特性が、集団での学習をさらに難しくしている場合もあります。
例えば、読字の困難さという一つのつまずきが、読書への抵抗感を生み、語彙力や知識の不足につながります。
その結果、国語だけでなく全ての教科で学業不振に陥り、最終的には不登校などの二次的な問題に発展してしまうケースも少なくありません。
この「困難の連鎖」を断ち切るためには、早期に、そして的確に、その子の特性に合った支援を始めることが何よりも重要なのです。
表1: 発達障害の主な種類と学習面での困りごとの例
| 障害の種類 | 主な特性 | 学習面での具体的な困りごと |
| 読字障害(ディスレクシア) | 文字を読むこと、単語を認識することに困難がある。 | ・文字や行を飛ばして読んでしまう ・音読がたどたどしい、またはひどく嫌がる ・読めても文章の意味が理解できない |
| 書字障害(ディスグラフィア) | 文字の形を認識し、正しく書くことに困難がある。 | ・マス目に合わせて文字が書けない ・鏡文字になる、似た形の字を間違える ・作文や板書が極端に苦手、または時間がかかる |
| 算数障害(ディスカリキュリア) | 数の概念、数量、計算、推論の理解に困難がある。 | ・繰り上がり、繰り下がりの計算ができない ・指を使わないと簡単な計算ができない ・文章問題で式を立てられない ・時計を読むのが苦手 |
| ADHD(注意欠如・多動症) | 不注意、多動性、衝動性の特性がある。 | ・授業中に集中力が続かない・ケアレスミスが多い ・計画的に課題を進めるのが苦手 |
| ASD(自閉スペクトラム症) | 対人関係、コミュニケーション、こだわりの特性がある。 | ・集団での指示が理解しにくい ・比喩や冗談が分からず、言葉通りに受け取る ・特定の学習方法に固執することがある |
発達障害のお子様に個別指導がもたらす5つのメリット
学校の集団授業では、どうしても一人ひとりの特性に合わせた対応が難しく、お子様が「分からない」という経験を積み重ねてしまいがちです。
そこで大きな力を発揮するのが「個別指導」です。
個別指導は、単に勉強を教えるだけでなく、お子様の学習に対するネガティブな連鎖を断ち切り、ポジティブな循環を生み出すことに効果的な学習支援方法です。
ここでは、個別指導がもたらす5つのメリットを解説します。
●メリット1
お子様一人ひとりのペースと特性に合わせた「オーダーメイド学習」
個別指導の最大のメリットは、カリキュラムを完全にお子様一人ひとりに合わせられることです。
学校の授業は決まったペースで進むため、一度つまずくと追いつくのは大変です。
しかし個別指導なら、例えば小学校3年生の算数でつまずいているのであれば、必要に応じて1年生の数の概念までさかのぼって学び直す「戻り学習」が可能です。
また、指導方法も柔軟に変えられます。
視覚的な情報処理が得意なASDのお子様には図やイラストを多用したり、集中力が続きにくいADHDのお子様には課題を5分程度の短い時間に区切って取り組んだりと、その子の特性に最も合った方法で学習を進めることができます。
これは、画一的な指導になりがちな集団授業では決して真似のできない、個別指導ならではの強みです。

●メリット2
「できた!」を積み重ねる。自己肯定感を育む成功体験
学校で「できない」経験を重ねてきたお子様にとって、何よりも大切なのが「自分にもできるんだ」という感覚を取り戻すことです。
個別指導は、この「成功体験」を意図的に作り出すのに最適な環境です。
指導者は、お子様の現在の能力を正確に見極め、「少し頑張れば達成できる」絶妙な難易度の課題(スモールステップ)を設定します。
昨日まで読めなかった漢字が一文字読めた、解けなかった計算問題が一問解けた。
その一つひとつの「できた!」という小さな成功体験が、お子様の心に自信の種をまき、学習への意欲を育てます。
この成功体験の積み重ねこそが、学校で傷ついてしまった自己肯定感を回復させるきっかけになります。

●メリット3
周囲を気にせず集中できる「安心できる学習環境」
多くの子どもがいる教室は、発達障害の特性を持つお子様にとって、時に刺激が多すぎる場所になり得ます。
周りの生徒の話し声や動きが気になって集中できなかったり、「自分だけできていない」と他の子と比較して不安になったりすることがあります。
個別指導、特に家庭教師やマンツーマンの指導では、そうした外部からの刺激が最小限に抑えられます。
他人の目を気にすることなく、分からないことを「分からない」と素直に言える。
間違えることを恐れずに挑戦できる。
この「安心感」に満ちた環境が、お子様の心をリラックスさせ、学習に集中するための土台となるのです。

●メリット4
先生との強い信頼関係が学習意欲を引き出す
1対1の指導形式は、お子様と先生との間に強い信頼関係を築きやすいという大きな利点があります。
集団授業では、先生は多くの生徒を見なければならず、一人ひとりと深く関わる時間は限られています。
しかし個別指導では、先生はお子様一人のためだけに時間を使います。
自分のことをしっかり見て、理解しようとしてくれる先生の存在は、お子様にとって大きな心の支えとなります。
この先生になら心を開ける、この先生のために頑張りたい。
そうした信頼関係が、学習へのモチベーションを引き出し、困難な課題にも粘り強く取り組む力を育むのです。

●メリット5
保護者も安心。密な連携と相談のしやすさ
お子様のことだけでなく、保護者の方自身の不安を軽減できるのも、個別指導のメリットです。
個別指導サービスでは、毎回の指導後に先生から直接、その日の学習内容や子どもの様子について詳しいフィードバックがあります。
「今日はこんな工夫をしたら集中できました」「この単元は理解が進んでいるので、ご家庭ではこんな声かけをしてみてください」といった具体的な報告は、家庭でのサポートのヒントになります。
また、保護者自身が抱える悩みや進路についての不安を、専門的な知識を持つ先生やスタッフに気軽に相談できる体制は、一人で悩みを抱えがちな保護者にとって、何より心強い味方となるでしょう。

これら5つのメリットは、それぞれが独立しているわけではありません。
むしろ、互いに深く関連し合い、強力な「好循環」を生み出します。
安心できる環境が子どもの心を開き、そこで先生との信頼関係が育まれる。
その信頼関係を土台に、オーダーメイドの学習が効果的に行われ、それが成功体験につながる。
その成果とプロセスが保護者との連携を通じて家庭でのサポートに活かされ、さらに子どもの安心感を強固にする。
このサイクルこそが、学校で陥りがちな「失敗と不安の悪循環」を断ち切り、お子様を成長へと導く原動力となるのです。
「個別指導」と「集団指導」の違いは?
個別指導のメリットを理解した上で、一般的な学習塾である「集団指導」と比較してみましょう。
どちらがお子様にとって最適かを判断するために、それぞれの長所と短所を客観的に把握することが大切です。
集団指導にも、他の生徒と切磋琢磨できる環境で学習意欲が高まったり、比較的費用が安価であったりといったメリットはあります。
しかし、発達障害の特性を持つお子様にとっては、デメリットが大きく上回ってしまうケースもあります。
以下の「個別指導」と「集団指導」の比較表をご覧ください。
表2: 「個別指導」と「集団指導」比較表
| 比較項目 | 個別指導 | 集団指導 |
| 学習ペース | ◎ お子様の理解度に合わせて、さかのぼったり、ゆっくり進めたりと自由自在。 | △ 決められたカリキュラム通りに進むため、一度つまずくと追いつきにくい。 |
| カリキュラム | ◎ 苦手な分野や特性に特化した、完全オーダーメイドの計画を作成可能。 | △ 全員共通のカリキュラム。個別のニーズへの対応は限定的。 |
| 講師の関わり | ◎ 1対1で常に見守り、きめ細やかな指導と声かけができる。 | △ 講師1人に対し生徒が多数のため、個別のサポートは不足しがち。 |
| 刺激の多さ | ◎ 周囲の視線や雑音がなく、学習に集中しやすい静かな環境。 | × 他の生徒の動きや会話が気になり、集中力が途切れやすい。 |
| 社会性 | △ 他の生徒との関わりが少ないため、協調性を育む機会は限られる。 | ○ 学校以外の友達ができ、切磋琢磨する中で社会性が育まれる可能性がある。 |
| 費用 | △ マンツーマンに近いほど料金は高くなる傾向。集団指導より月1~2万円程度高いことも。 | ◎ 個別指導に比べて費用は比較的安価。 |
この表からわかるように、「どちらが優れているか」という単純な話ではありません。
重要なのは、「今のお子様の目的に合っているのはどちらか」という視点です。
例えば、学習の遅れが大きく、自信を完全に失っている状態のお子様にとっての最優先課題は、「基礎学力の定着」と「自己肯定感の回復」です。
この目的のためには、個別指導が適していると言えるでしょう。
一方で、ある程度学習が軌道に乗り、次のステップとして「集団でのルールを学ぶ」「他者と協力する」といった社会性を身につけさせたいと考えるならば、少人数制のグループ指導などを検討する段階が来るかもしれません。
このように、お子様の状態や目的に合わせて、最適な学習形態を選ぶという発想が大切です。
個別指導が育む「自己肯定感」
個別指導の目的は、単にテストの点数を上げることや、苦手科目を克服することだけではありません。
その最も価値ある成果は、お子様の心の中に「自己肯定感」という一生の財産を育むことにあります。
学校の集団生活の中で、「みんなと同じようにできない」という経験を繰り返すことは、子どもの心に「自分は能力が低いんだ」という無力感を刻み込んでしまうことになります。
この自己肯定感の低下こそが、学習意欲を奪い、挑戦する気力を失わせる最大の敵です。
個別指導の指導者は、お子様が決して失敗しないように、目標を非常に小さく分解する「スモールステップ」という手法を用います。
例えば、「宿題を全部やる」ではなく、「まず漢字の書き取りを3つだけやってみよう」というように。
そして、その小さな目標をクリアできた時、「すごい!最後まで集中して書けたね!」と、結果だけでなく努力のプロセスを具体的に褒めます。
この「小さな成功」と「的確な承認」の繰り返しが、「やればできるんだ」という確かな自信を少しずつ、しかし着実に育てていきます。
個別指導は、お子様の学習のための「リハビリ期間」と捉えることもできます。
個別指導でスキルと自信をつけることで、お子様は再び集団の場に戻った時に、以前よりもずっとうまく対応できる力を身につけることができるのです。
無料相談
まずはご相談ください